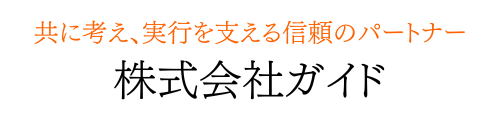AI初心者の私が「ChatGPT導入支援」を始めた理由
目次
ChatGPTって、なんとなく使ってた。そんな私が、本気で向き合うことにした理由。
「AIって難しそう」
「ChatGPTって、一部の人だけが使ってるんでしょ?」
…そんなふうに感じている人、多いんじゃないでしょうか。
正直に言えば、私も昨年起業するまで、“なんとなく”使っていた側の人間でした。
ChatGPTの存在自体は、起業する前から知っていましたし、無料版で軽く使ったこともありました。
ただ、その頃は遊び半分というか、ちょっと気になったことを聞いてみる程度。
「便利そうだな」とは思いつつも、積極的に情報を集めたり、活用の幅を広げようとしたことはありませんでした。
そんな私が、ChatGPTの有料版(Plusプラン)に登録して、本格的に使い始めたのは、起業してから。
メールの文面を整えたり、文章を要約したり、DMやチラシの下書きを手伝ってもらったり…。
よくある使い方ですが、実際に業務の中で使ってみると、
「これ、もっと使いこなせたら、めちゃくちゃ助かるかも」と感じる場面が増えていきました。
そして、それを確信に変えてくれたのが、2025年1月に開催されたAI博覧会でした。
AIツールの“裏側”を見て、やっと本当の意味で気づいたこと。
2025年1月22日と23日、大阪で開催された「AI博覧会」に実際にどんなツールがあるのかを自分の目で確かめたくて、情報収集も兼ねて足を運びました。
AIを活用した最新のビジネスツールや生成AIが多数展示されていて、実務者目線でも「これはすぐ使える」と感じるものが多くありました。
その中で特に印象的だったのは、多くのツールの裏側にChatGPTが組み込まれていたということ。
議事録の自動作成、リアルタイム翻訳、チャットボット、業務アシスタント……
パッと見では“独自AI”のように見えるそれらも、技術の中心にはChatGPTのAPIやモデルが使われていました。
あらためて気づいたのは、ChatGPTが単なるツールではなく、生成AI市場そのものの“基準”になっているということです。
実際、GoogleのGemini(旧Bard)やMicrosoftのCopilotといった競合も、ChatGPTをベンチマークにしながら開発が進められているのは明らかです。
さらに今も、新しいAIが登場したりアップデートされるたびに、 「ChatGPTと比べてどうか」という視点がほぼ必ずと言っていいほど語られています。
つまり、ChatGPTは“比較対象”であると同時に、“共通語”でもある。
この構造が見えたことで、「まずはここから慣れておくことが、将来的にも大きな価値になる」と私は強く感じました。
そして、もうひとつ考えさせられたことがあります。
今のところ、ChatGPTは個人で使っている人や、大企業・先進企業の一部が導入している状況が多いです。
でも、それだけでは不十分だと思うのです。
地方企業や中小企業こそ、この流れに取り残されてはいけない。
人手不足、働き方改革、そしてDX。
どれも避けては通れない今の時代に、比較的安価で、すぐにでも試せるChatGPTは“最初の一歩”として非常に現実的な選択肢ではないでしょうか。
展示会から戻る頃には、私は「この流れをもっと地域の企業にも伝えたい」と思うようになっていました。
私は専門家じゃない。でも、それが強みになると思っている。
ChatGPTの導入支援と聞くと、 「AIの専門家なんですか?」とか 「エンジニアとして活動していたんですか?」と聞かれることがあります。
実はそうではありません。
私はAIの開発者でもなければ、プログラミングができるわけでもない。
ChatGPTについても、起業後に業務で使いながら、少しずつ理解を深めてきた立場です。
だからこそ、最初につまづく気持ちが、すごくよく分かります。
- 何を聞けばいいか分からない
- 思った通りに返ってこないと、使いこなせていない気がする
- このまま続けても意味があるのか分からない
そんな“もやもや”を、私自身も経験してきました。
でも、だからこそ今、私にできる役割があると思っています。
ChatGPTに関する情報を“専門用語”ではなく、
実務レベルの言葉に置き換えて届けること。
高度な技術解説ではなく、
「それ、こう使えば便利ですよ」と伴走すること。
それが今の私にとっての、導入支援という仕事の軸です。
実際、多くの地方企業では、導入のハードルは「使えるかどうか」ではなく、
「最初の一歩を誰と踏み出すか」だったりします。
ChatGPTはすごいツールです。
でも、それをどう使うかは“人のサポート”次第。
そして私が目指しているのは、“便利”を“使える”に変える、橋渡しのような存在です。
だから、まだ使ったことがなくても、怖がる必要はありません。
一緒に試しながら、少しずつ慣れていけるサポートを、私は用意しています。
ChatGPTでできることは、意外と“すぐそこ”にある。
ChatGPTと聞くと、「AIがすごいことをやってくれるんでしょ?」という印象を持たれがちです。
でも、実際に使ってみて思うのは──
本当に役立つのは、“特別な業務”より“日常のちょっとした仕事”の中だということ。
ChatGPTは、特にこんなときに力を発揮します
文章を考えるのが大変なとき
- メールの返信文
- DMやチラシの文章案
- SNS投稿文のたたき台
- キャッチコピーの候補出し
長い文章や情報を整理したいとき
- 会議メモや記事の要点整理
- 表現の言い換え(やさしい言葉に変換など)
- 書類や提案文のリライトサポート
アイデアを広げたいとき
- 新商品のネーミング案
- サービス説明の表現バリエーション
- チラシやブログ構成の下書きづくり
しかも、使い方は驚くほどシンプルです。
たとえば、こんなふうに話しかけるだけ。
「高齢者向けにやさしい表現で言い換えて」
「この長文を短く要約して」
「SNS投稿に使えるキャッチコピーを3案考えて」
「サービスのメリットを3つに分けて説明して」
むずかしい操作や専門知識はいりません。
社員に「これちょっとお願い」と頼むような感覚で使えるのが、ChatGPTの最大の強みです。
今は大企業や、一部の先進的な企業だけが使っているように見えるかもしれません。
でも、本当は──
地方企業にこそ、ChatGPTのような“使いやすくて安価なツール”が必要なんじゃないかと感じています。
実際、こうした活用を少しずつ取り入れるだけで、
「考えるのに時間がかかっていた仕事」が「10分で終わる仕事」に変わる。
それだけでも、日々の業務の負担はかなり軽くなります。
このように、“よくある仕事”にこそ、ChatGPTは役に立ちます。
最初の一歩は、特別なことじゃなくていいんです。
「試してみる」「一つやってみる」──それが大きな変化のきっかけになります。
最初の一歩を、一緒に。
私はAIの専門家でも、ChatGPTのマニアでもありません。
でも、自分自身が“初心者寄り”の立場で使い始めたからこそ、
「最初のつまずき」や「戸惑いのポイント」がよく分かります。
そして、展示会での気づきや、自分の業務での活用を通して思ったのは──
ChatGPTは、一部の企業だけが使う“特別なツール”ではなく、今後の働き方に欠かせない“共通言語”になっていく存在だということです。
とくに地方や中小企業にとって、
人手不足、業務の属人化、働き方改革など、避けられない課題があります。
そんな時代だからこそ、比較的手軽に始められて、実務に使えるChatGPTは、
「とりあえずやってみる」にちょうどいい、第一歩のツールだと思うんです。
ChatGPTは、完璧に使いこなす必要はありません。
むしろ、「これって使えるかも」と気づいたり、
「ちょっと試してみたいな」と思うことからすべてが始まります。
もし「少し話を聞いてみたい」「試しに相談だけでも…」という方がいれば、
簡単な無料相談も受け付けています。
実際の業務やお悩みに合わせて、一緒に考えていけたら嬉しいです。
お問い合わせはこちらから
📩 guide-2024@outlook.com
お問い合わせフォームにて
※「相談です」と一言添えていただければ、お気軽にお話しできます。